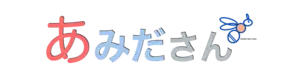景品抽選の法的注意点【景品表示法・公正取引委員会ガイドライン完全解説】
「会社のイベントで景品抽選をしたいけど、法律的に大丈夫?」 「SNSキャンペーンの景品に上限額はある?」
企業が景品抽選を実施する際には、景品表示法という法律を守る必要があります。違反すると、罰金や社会的信用の失墜につながる可能性も。
この記事では、景品抽選の法的ルールを分かりやすく解説します。
本記事の参考情報源
この記事は、以下の公式情報源を基に作成しています:
消費者庁(公式):
公正取引委員会(公式):
重要: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の案件については、必ず消費者庁、公正取引委員会、または景品表示法に詳しい弁護士にご相談ください。
景品表示法とは
法律の目的
正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
目的:
- 消費者の利益を保護する
- 公正な競争を確保する
- 過大な景品による不当誘引を防止する
管轄: 消費者庁・公正取引委員会
「景品」の定義
景品表示法における「景品」とは、以下の3要件を満たすものです:
顧客誘引のため
- 商品・サービスの販売促進が目的
事業者が提供する
- 企業や個人事業主が提供
経済的利益
- 金品、サービス、その他経済的価値があるもの
景品に該当する例:
- 商品券、ギフトカード
- 家電製品、食品
- 旅行券
- ポイント、クーポン
景品に該当しない例:
- 商品のサンプル(正常な商慣習の範囲内)
- 値引き
- アフターサービス(通常の商取引の一部)
景品の種類と規制
景品は大きく3種類に分類され、それぞれ異なる規制があります。
1. 一般懸賞(抽選型キャンペーン)
定義: 商品・サービスの購入者や利用者を対象に、くじ等の偶然性により景品を提供する。
法的根拠: 昭和52年公正取引委員会告示第3号「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」
例:
- 「商品購入者の中から抽選で100名様にプレゼント」
- 「応募者の中から抽選で1名様に海外旅行」
- SNSフォロー&リツイートキャンペーン(購入条件付きの場合)
景品の上限額:(消費者庁公式情報より)
| 取引価額 | 景品の最高額 | 総額の上限 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞売上予定総額の2% |
具体例:
- 1,000円の商品 → 最高額 20,000円
- 10,000円の商品 → 最高額 100,000円
注意点: 「総額の上限2%」も同時に満たす必要があります。
2. 共同懸賞
定義: 複数の事業者が共同で実施する懸賞。
法的根拠: 昭和52年公正取引委員会告示第3号「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」
例:
- 商店街全体でのスタンプラリー
- 複数企業合同のキャンペーン
- ショッピングモール全体の抽選会
景品の上限額:(消費者庁公式情報より)
| 取引価額 | 景品の最高額 | 総額の上限 |
|---|---|---|
| 制限なし | 30万円 | 懸賞売上予定総額の3% |
一般懸賞より緩い理由: 複数事業者が共同で行うため、特定の事業者だけが有利にならない。
3. オープン懸賞(誰でも応募可能)
定義: 商品・サービスの購入を条件としない懸賞。
法的根拠: 景品表示法上の規制対象外(購入を条件としないため)
例:
- 「どなたでも応募可能!抽選で○○プレゼント」
- 来店者全員が対象の抽選会(購入不要の場合)
- アンケート回答者への景品(購入不要の場合)
景品の上限額:(消費者庁公式情報より) 制限なし
理由: 購入が条件でないため、不当な顧客誘引にならない。
注意: 「購入した方は当選確率2倍」などは一般懸賞に該当するため規制対象。
違法となるケース
ケース1: 景品額の上限超過
違反例: 1,000円の商品を購入した人の中から抽選で「20万円の旅行券」
理由:
- 取引価額: 1,000円
- 上限: 1,000円 × 20倍 = 20,000円
- 実際: 200,000円 → 10倍も超過
正しい対応:
- 20,000円以下の景品にする
- または商品を5,000円以上にして上限10万円を適用
ケース2: 総額上限の超過
違反例: 懸賞売上予定総額 1,000万円のキャンペーンで、景品総額300万円
理由:
- 上限: 1,000万円 × 2% = 20万円
- 実際: 300万円 → 15倍も超過
正しい対応:
- 景品総額を20万円以下にする
- または当選者数を増やして1人あたりの額を下げる
ケース3: 必ず当たる懸賞の誤認
違反例: 「全員にプレゼント!」と表示しているが、実際は抽選で一部の人のみ
理由:
- 優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)
- 消費者を誤認させる不当表示
正しい対応:
- 「抽選で○名様にプレゼント」と正確に表示
- 当選確率を明記
ケース4: 二重価格表示
違反例: 「通常価格10,000円→特別価格3,000円」だが、通常価格で販売した実績がない
理由:
- 有利誤認表示
- 実際より有利だと誤認させる
正しい対応:
- 実際の販売実績がある価格のみを表示
- または「参考価格」と明記
社内イベント・非営利イベントの場合
社内懇親会・忘年会
景品表示法の適用: 適用されない(顧客誘引目的でないため)
例:
- 会社の忘年会での景品抽選
- 社員旅行の抽選会
- 社内運動会の賞品
注意点:
- 金額制限はないが、常識的な範囲で
- 税務上の問題(給与課税)に注意
- 社内規定を確認
NPO・ボランティア団体
景品表示法の適用: 営利目的でなければ適用されない
例:
- NPOの参加者向け抽選
- 地域イベントの景品
- 学校のバザー
注意点:
- 実質的に商業活動であれば適用される可能性
- 寄付金や会費との関係を明確に
学校行事
景品表示法の適用: 適用されない
例:
- 学校の文化祭での抽選
- クラスイベント
- 部活動の景品
コンプライアンスチェックリスト
イベント企画段階
- イベントの目的は明確か(顧客誘引か、社内イベントか)
- 景品表示法の適用対象かを確認
- 懸賞の種類(一般懸賞・共同懸賞・オープン懸賞)を特定
- 取引価額を正確に算出
- 景品の最高額が上限内か確認
- 景品の総額が上限内か確認
広告・告知段階
- 応募条件を正確に表示
- 当選者数・当選確率を明記
- 「必ず当たる」などの誤認表現を避ける
- 景品の内容を具体的に記載
- 応募期間・抽選日を明示
抽選実施段階
- 公平な抽選方法を採用
- 抽選プロセスの透明性を確保
- 当選者の発表方法を事前に明示
- 個人情報保護法の遵守
事後対応
- 当選者への連絡を迅速に
- 景品の配送・提供を確実に
- 記録を保存(3年間推奨)
- クレーム対応体制の整備
違反した場合の罰則
法的根拠: 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
行政処分
措置命令(景品表示法第7条):(消費者庁公式情報より)
- 違反行為の差し止め
- 再発防止策の実施
- 一般消費者への周知
課徴金(景品表示法第8条):
- 違反売上の3%
- 対象期間: 最大3年間
例: 年間売上1億円の商品での違反 → 課徴金: 1億円 × 3% = 300万円
刑事罰
故意の違反(第36条):
- 2年以下の懲役
- または300万円以下の罰金
- またはその両方
法人処罰(第37条): 法人にも3億円以下の罰金
社会的影響
- 企業イメージの低下
- メディアによる報道
- 取引先からの信頼喪失
- 採用活動への悪影響
適法に景品抽選を実施するためのポイント
ポイント1: オープン懸賞の活用
メリット:
- 景品額の上限がない
- 規制が緩やか
- 広くアピールできる
デザイン例: 「商品購入の有無にかかわらず、どなたでも応募可能」
ポイント2: 景品額を抑える
1,000円以下の商品: 景品の上限は20,000円
5,000円以上の商品: 景品の上限は100,000円
戦略: 高額景品1つより、中額景品を複数用意する
ポイント3: 共同懸賞の検討
複数企業で共同実施すれば:
- 景品の上限が30万円に
- 総額上限も3%に
ポイント4: 専門家への相談
不安な場合は:
- 弁護士(景品表示法専門)
- 公正取引委員会への照会
- 業界団体のガイドライン確認
よくある質問
Q1: 社内イベントなら何でもOKですか?
A: 基本的にOKですが、以下に注意:
- 税務上の問題(高額すぎると給与課税の可能性)
- 社内規定の確認
- ハラスメントにならないよう配慮
Q2: SNSキャンペーンは規制対象ですか?
A: ケースバイケースです:
- フォロー&RTだけ → オープン懸賞(上限なし)
- 商品購入者限定 → 一般懸賞(上限あり)
Q3: 当選確率を明示しないとダメですか?
A: 法律上の義務はありませんが、明示を強く推奨:
- 消費者庁の指針で推奨
- トラブル防止
- 信頼性向上
Q4: 個人事業主のイベントも規制対象ですか?
A: はい、事業者であれば対象です。
- 法人か個人かは無関係
- 事業として実施していれば適用
Q5: 外国企業が日本でキャンペーンする場合は?
A: 日本国内の消費者が対象なら日本の景品表示法が適用されます。
まとめ
景品抽選の法的ポイント:
規制の対象:
- 顧客誘引目的の景品提供
- 事業者が実施するもの
景品の種類と上限:
- 一般懸賞: 最高10万円(または取引価額の20倍)
- 共同懸賞: 最高30万円
- オープン懸賞: 上限なし
違反のリスク:
- 課徴金(売上の3%)
- 刑事罰(2年以下の懲役等)
- 社会的信用の失墜
安全な実施方法:
- オープン懸賞の活用
- 景品額を抑える
- 透明性の高い抽選方法を採用
- 事前に専門家に相談
法律を守りつつ、公平で盛り上がる抽選を実現しましょう!
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的な案件については、必ず弁護士や公正取引委員会にご相談ください。